更新日:2024年12月17日
ページID:1808
ここから本文です。
おもな食中毒微生物一覧
腸管出血性大腸菌
特徴
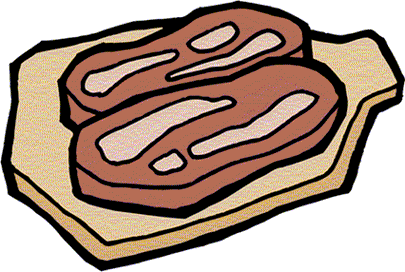 大腸菌は、家畜や人の腸内にも存在します。ほとんどのものは無害ですが、このうちいくつかのものは、人に下痢等の消化器症状や合併症を起こすことがあり、病原大腸菌と呼ばれています。病原大腸菌の中には、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす腸管出血性大腸菌と呼ばれるものがあります。
大腸菌は、家畜や人の腸内にも存在します。ほとんどのものは無害ですが、このうちいくつかのものは、人に下痢等の消化器症状や合併症を起こすことがあり、病原大腸菌と呼ばれています。病原大腸菌の中には、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす腸管出血性大腸菌と呼ばれるものがあります。
腸管出血性大腸菌は、菌の成分(「表面抗原」や「べん毛抗原」等と呼ばれています)によりさらにいくつかに分類されています。代表的なものは「腸管出血性大腸菌O157」で、そのほかに「O26」や「O111」等が知られています。
腸管出血性大腸菌の産生する毒素はベロ毒素と呼ばれ、毒性が非常に強く、重い症状が現れます。高齢者、乳幼児、免疫力の低下している人では、重症化したり死亡する恐れがあります。
主な感染源
加熱不足の食肉やレバー、肉の生食など
腸管出血性大腸菌に汚染された水や野菜などの食品
腸管出血性大腸菌に汚染された手指や調理器具を介した二次汚染
潜伏時間
3~8日
主な症状
激しい腹痛、水様性下痢、血便など
重症化すると、溶血性尿毒症症候群(HUS)や、脳症などの合併症
予防のポイント
- 腸管出血性大腸菌は加熱に弱いため、十分に加熱(75℃以上1分間以上)しましょう。
- 食材は、十分に洗浄しましょう。特に生で食べる野菜は、流水で十分に洗浄して、汚れと一緒に細菌を洗い流しましょう。葉物の場合は内側もよく洗いましょう。
- 肉やレバーなどは、10℃以下で保存しましょう。
- 二次汚染を防止するために、手洗いを徹底し、調理器具や食器などはしっかり洗浄・殺菌しましょう。
(厚生労働省)腸管出血性大腸菌O157等による食中毒(外部サイト)
カンピロバクター
特徴
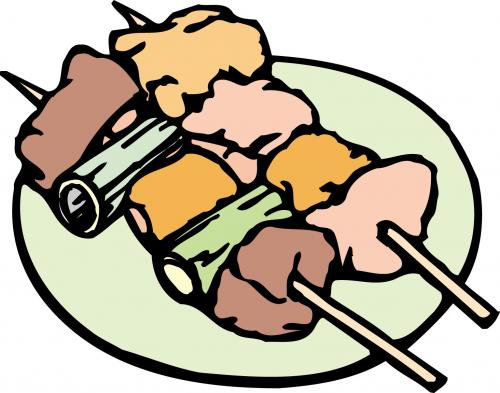 鶏、豚、牛やペットなどの腸管内にいる菌で、中でも鶏は高率に保有しています。
鶏、豚、牛やペットなどの腸管内にいる菌で、中でも鶏は高率に保有しています。
熱や乾燥に弱く、常温の空気中でも徐々に死滅しますが、他の食中毒菌と比べて少量の菌でも食中毒を起こします。
主な感染源
加熱不足の食肉(特に鶏肉)など
生肉などを扱った調理器具や手指などからの二次汚染
潜伏時間
2~3日
主な症状
腹痛、下痢、発熱、頭痛、吐き気など
予防のポイント
- カンピロバクターは熱に弱いため、十分に加熱(75℃以上1分間以上)しましょう。
- 鶏肉などは、10℃以下で保存しましょう。
- 手洗いを徹底し、二次汚染を防止するために、調理器具や食器などはしっかり洗浄・殺菌しましょう。
(厚生労働省)カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)(外部サイト)
サルモネラ
特徴
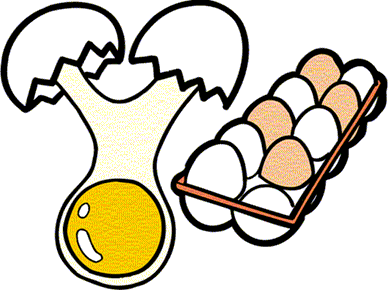 鶏、豚、牛、ペットや、は虫類、両生類、鳥類など、多くの動物が保有しています。
鶏、豚、牛、ペットや、は虫類、両生類、鳥類など、多くの動物が保有しています。
特に、鶏の腸管内にいる菌に汚染された鶏肉や卵が感染源となり、食中毒を起こすことが多くなっています。また、鶏の卵は、殻の中身が汚染されていることもあり、これを原因として食中毒が起こることもあります。
主な感染源
卵やその加工品(自家製マヨネーズやカスタードクリームなど)、鶏肉、豚肉など
生肉などを扱った調理器具や手指などからの二次汚染
潜伏時間
8~48時間
主な症状
激しい下痢、腹痛、嘔吐、発熱など
予防のポイント
- サルモネラは熱に弱いため、十分に加熱(75℃以上1分間以上)しましょう。
- ひび割れた卵を使うのは避けましょう。
- 鶏肉、卵などは、10℃以下で保存しましょう。
- 手洗いを徹底し、二次汚染を防止するために、調理器具や食器などはしっかり洗浄・殺菌しましょう。
腸炎ビブリオ
特徴
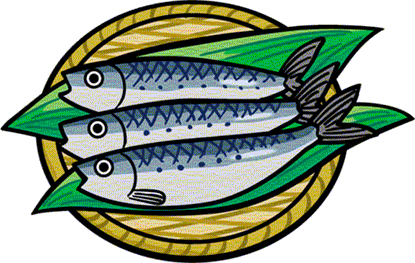 塩分を好む細菌であり、海水や海中の泥の中に潜み、魚介類に付着して感染源となります。
塩分を好む細菌であり、海水や海中の泥の中に潜み、魚介類に付着して感染源となります。
海水温が20℃を超えると大量に増殖するため、海水温が上がる夏期(6月~9月)、特に猛暑の年は食中毒の発生が急増します。15℃以下では増殖が抑制されますが、20℃以上では、他の細菌と比べて増殖するスピードがとても速いため、夏期は特に注意が必要です。
主な感染源
刺身や寿司などの、生食用海産魚介類
魚介類を扱った調理器具や手指などからの二次汚染
潜伏時間
10~24時間
主な症状
上腹部の激しい腹痛と水溶性下痢、吐き気、嘔吐、発熱など
予防のポイント
- 腸炎ビブリオは真水に弱いため、魚介類は流水(真水)でよく洗いましょう。
- 十分に加熱(65℃以上1分間以上)しましょう。
- 魚介類は4℃以下で保存し、室温放置しないようにしましょう。
- 冷蔵庫から出したら、2時間以内に食べましょう。
- 手洗いを徹底し、二次汚染を防止するために、調理器具や食器などはしっかり洗浄・殺菌しましょう。
黄色ブドウ球菌
特徴
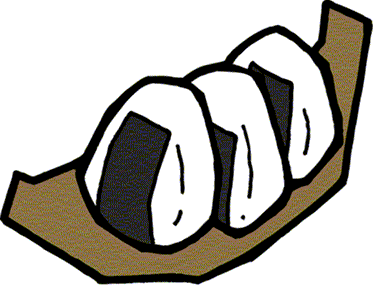 人の鼻や皮膚、特に傷口やニキビなどの化膿した部分に存在します。
人の鼻や皮膚、特に傷口やニキビなどの化膿した部分に存在します。
黄色ブドウ球菌は、食品中で増殖するときに毒素をつくり、その毒素により食中毒が起こります。黄色ブドウ球菌は熱に弱いですが、毒素は非常に熱に強いため、通常の加熱では分解されません。
主な感染源
調理者の手を介して汚染した食品(おにぎりなど)
潜伏時間
約3時間
主な症状
激しい嘔吐、吐き気、腹痛、下痢など
予防のポイント
- 手をよく洗いましょう。
- 手指に傷があるときは調理しないか、使い捨ての手袋をしましょう。
- 食品は10℃以下で保存し、調理後はすぐに食べましょう。
ウェルシュ菌
特徴
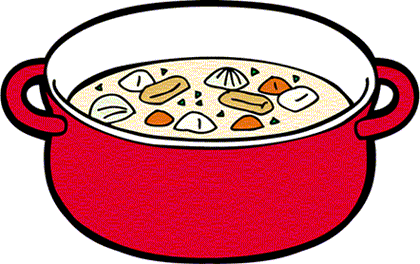 人や動物の腸管内、土壌、水中など自然界に広く分布し、酸素が少ない環境を好みます。牛、豚、鶏などの糞便や魚から検出されますが、健康な人の便からも検出されます。食品では特に食肉(牛、豚、鶏肉など)の汚染が高いです。
人や動物の腸管内、土壌、水中など自然界に広く分布し、酸素が少ない環境を好みます。牛、豚、鶏などの糞便や魚から検出されますが、健康な人の便からも検出されます。食品では特に食肉(牛、豚、鶏肉など)の汚染が高いです。
この細菌は熱に強い芽胞を作るため、高温でも死滅せず生き残ります。そのため、食品を大釜などで大量に調理すると、他の細菌が死滅してもウェルシュ菌の耐熱性の芽胞は残存し、食品の中で大量に増殖します。ウェルシュ菌は、人の体内で毒素をつくり、その毒素により食中毒が起こります。
主な感染源
肉類、魚介類、野菜およびこれらを使用した煮物や、カレー、シチュー、スープなどのように、大量に加熱調理され、大きな器に入ったまま室温で放冷されていた食品など
潜伏時間
6~18時間
主な症状
腹痛、下痢
予防のポイント
- 前日調理、室温放置は避け、加熱調理したものはすぐに食べましょう。
- 一度に大量の食品を加熱調理したときは、小分けするなど工夫して急速に冷却しましょう。
ノロウイルス
特徴
 ノロウイルス食中毒は冬期に多発し、非常に感染力が強く、ごく少量のウイルスで発病します。
ノロウイルス食中毒は冬期に多発し、非常に感染力が強く、ごく少量のウイルスで発病します。
ノロウイルス感染者の便や嘔吐物には多量のノロウイルスが含まれるため、二枚貝の生食の他、二次汚染(汚れた手などを介して食品を汚染すること)なども食中毒発生の原因となります。
また、食品を介してだけではなく、人から人への二次感染による集団発生も起こります。
主な感染源
二枚貝の生食
調理者の手を介して汚染された食品
潜伏時間
24~48時間
主な症状
吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱など
予防のポイント
- 生鮮食品(野菜、果物など)は十分に洗浄しましょう。
- カキなどの二枚貝が感染源になることがあるので、二枚貝の取扱いには十分注意し、中心部まで加熱調理(85~90℃で90秒以上)して食べましょう。
- ノロウイルスはアルコール消毒には抵抗性があるため、まな板など調理器具は、十分に洗浄した後、熱湯や塩素系殺菌剤で消毒をしましょう。
- 下痢や風邪に似た症状がある場合には、調理に従事しないようにしましょう。
- 外出先から帰宅した後、トイレの後、調理の前、食事の前には石けんを使ってよく手を洗いましょう。
- 嘔吐物、排泄物などを処理する場合は、直接触れないようにしましょう。もし、触れた場合には、石けんを使ってよく手を洗いましょう。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください